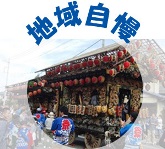掲載中「河内ふるさと探訪・岡本あれこれ」の(35)申内の天祭
書き出しに「鹿沼から購入されたと伝承があります」とありますが、令和6年(2024年)1月13・14日の調査組立によって、「申内で製作された」という結果がでましたのでご報告・訂正をさせて頂きます。
| 申内の天棚 調査報告書に基づく背景 |
【調査に至った経緯】
群馬県伊勢崎市の個人所蔵の屏風に下張りされていた古文書群(300枚以上あると思われる)の中に彫物師 弥勒寺音八が所有していた反古紙*と考えられる物が発見されました。
その中で、令和元年(2019年)に発見された手紙に「岡本村の仕事が出来ましたので、少々の仕事で今は石井川岸におります。」という内容の一文があります。
「岡本村の仕事」とは何を指しているかを調べたところ、白沢町の住吉晴氏が書かれた本『河内町の屋台と天棚』(平成18年発行)の申内天棚のページに「竜の絵に「梅雪」の銘がある」とあり、「梅雪」は弥勒寺音八が俳句や絵画に使用していた名前であることから、申内の天棚は弥勒寺音八が製作した可能性が考えられた。
その為、調査組立の依頼を受け、36年ぶりに天棚の組み立てが行なわれました。
*反古紙とは、書き損じや不要になった紙のこと。現在で言うリサイクルする紙。
【調査の結果】
製作年代・・・古文書と天棚の墨書から、申内の天棚は嘉永元年(1848年)ごろから嘉永6年(1853年)にかけて製作されたと考えられる。
*完成したと思われる嘉永6年って?・・・ペリー来航。第12代将軍徳川家慶死去。
製作者・・・・彫刻に作者銘は確認できなかったものの、「音八・下張り文書」に記載された特徴的な彫刻と実際の天棚彫刻がほぼ一致したこと・彫刻の作風・梅雪の銘のある天井画から彫刻の製作は弥勒寺音八と考えられる。
【弥勒寺音八】文政4年(1821年)~明治20年(1887年)没
現在の群馬県伊勢崎市境下渕名の彫刻師。
宮大工の棟梁、弥勒寺音次郎(1796~1869)の長男として生まれる。
本名は幸孝。天保13年(1842年)の頃に音次郎が小林から弥勒寺に改姓したとされる。
国指定重要文化財 笠間稲荷神社本殿の彫刻が有名。
皇居の明治造営の際、賢所の車寄せの菊花紋の彫刻を拝命。
栃木県内で弥勒寺音八の製作物は初見という貴重な天棚であることが判明しました。
文責:申内天棚保存会 仲山初枝(申内天棚報告書及び境歴史資料246号より一部抜粋)